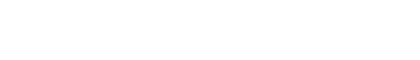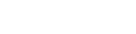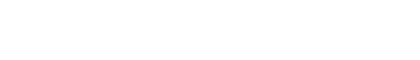炊飯機の便利な予約機能。夜に炊飯予約をしたら朝までお米が水に浸かったままだけど大丈夫?
2024.03.26

朝に炊き立てのご飯が食べたい場合、前日の夜に炊飯器にお米と水を入れて予約機能を使っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、長時間水につけたままになるため「味に影響するのではないか」「食中毒は大丈夫なのか」と気になりますよね。
気になっても夜中に起きたり、早起きしたりするのはできれば避けたいところです。
そこで今回は、長時間お米を水につけると考えられる影響やおいしく炊くコツなどをくわしく解説します。
1.夜に炊飯予約をして水につけたままのお米は大丈夫?
1-1.説明書に記載されている予約時間までであれば基本的には大丈夫
浸水によるお米の腐敗を防ぐために、炊飯器の説明書には「◯◯時間以内に設定してください」という記載があります。基本的には炊飯器の説明書に記載されている予約時間までであれば、水につけておいても問題はありません。
1-2.長過ぎる浸水時間はおいしさに影響も
通常、お米は30分から1時間ほど水に浸けてから炊くのがベストです。浸水時間が長すぎると、ご飯がべちゃっと柔らかくなってしまう恐れがあります。
夏場は8時間以上、冬場は13時間以上になると、お米が発酵してニオイの原因になるといわれています。
1-3.夏場は特に注意が必要
水温が高くなる夏場は、3~4時間後に炊飯が始まるようにセットした方がいいでしょう。炊飯時は100℃まで煮沸されますが、加熱で殺菌されない菌も存在します。

2.安全に炊飯器の予約機能を使うには
2-1.内釜などは日々お手入れをする
衛生面が気になるのであれば、お米や水、吸水時間に気を配るだけではなく、炊飯器もきれいな状態を保ちましょう。
内釜は使うたびに洗い、炊飯器本体やその他の部品も説明書を見て、こまめにお手入れをしてください。
2-2.氷を入れておく
夏場に水温が高くなってしまいそうなときは、氷を入れるといいでしょう。
お米をといだら、先に氷を入れてから冷たい水を水位線まで入れてください。先に氷を入れることで、水の量が増えてしまうのを防ぎ、水温が低い状態を長く保てます。
菌の増殖を防ぐために、酢や梅干しを入れるという人もいますが、内釜を傷める可能性や炊飯器の部品などが故障するなどのトラブルが起こる場合もあるため、控えてください。
2-3.炊きあがり時間を早め、保温時間を多めに取る
お米の浸水時間が長くなるのを避けるために、炊飯する時間を早め、保温時間を多めに取るのもおすすめです。
ただし、保温時間も長いと、水分が抜けて味が落ちたり、食感が悪くなったりするため、長くても5~6時間までにしてください。
2-4.冷蔵庫で浸水させ、早炊きモードで炊く
予約機能を使用せずに炊き立てを食べる方法もあります。
前日の夜にお米を洗い、水を入れたら内釜ごと冷蔵庫に入れておき、朝起きてすぐに早炊きモードで炊飯する方法です。
水の温度が低い方がゆっくりと吸水されるため、お米に均一に水分がいきわたり、ふっくらと炊き上がります。
まとめ
基本的に炊飯予約ができる時間までは、お米を浸水しても問題はないとされていますが、味が落ちる可能性が考えられます。
朝、おいしい炊き立てのご飯が食べたいときは、炊飯器を清潔に保ち、水温が上がらないように氷を入れるなどの工夫をしましょう。
夏場は気温が高いため、不安な思いをしながら炊飯予約をするよりも、早炊きの方が安心かもしれませんね。
この記事でご紹介した内容は、家電製品に関連する一般的な情報をまとめたものであり、全てのメーカー、全ての製品に該当する内容ではございません。また、各メーカーや製品によって定められた取扱方法やメンテナンス方法と異なる対応をした場合は、安全性や品質保証を損なう可能性もございます。詳細はメーカーのサポートセンター、 またはプロの技術者にご相談していただくことを推奨いたします。